握り続けるナースコール

いつぞや、晩御飯が終わるころ、母が持ってきたのは、”横浜のおじさん”の手記だった。部屋の片付けをしている時に見つけたのだという。B5のコピー用紙の片面に2ページづつ白黒で印刷されただけのもので、タイトルは「握り続けるナースコール」とある。
横浜のおじさんは母のおじにあたり、私が小学校の4年生くらいのころ母と横浜まで会いにいったことがある。数えてみればもう30年くらい前のこと。
暑く眩しい夏、道中の並木道では蝉が鳴いていた。鹿児島からやってきた母と私を出迎えてくれたのは、その奥さんである”横浜のおばさん”だった。門扉をくぐり家のに入ると、玄関の照明器具、フローリング、階段、ソファー、キッチン、洋式トイレ、お上品な犬など、どれも田舎の古い家屋で暮らしていた私にとって縁遠いものばかりで、知らない国に来たかのようだった。リビングの隣の部屋にゆく。部屋の真ん中に大きなベッドが置かれていて、プスープスーと空気が膨らんだり縮んだりする音がしている。ベッドの近くまでいき背伸びをして覗きこむと骨格のしっかりしたおじさんが目をあけて寝ていた。横浜のおじさんである。横浜のおばさんが「鹿児島からイクコさんとノブアキくんが来てくれましたよ」とおじさんに話しかけると、母も「おじさんお久しぶりです」と大きな声で話しかけた。おじさんは動かず、声も出さす、目だけをぱっちり開けていて、正面につけられた画面に目で文字を打ちコミュニケーションを取る。私も母にうながされ、ぎこちなく挨拶をしたら「よくきたね」と優しい言葉を画面に書いてくれた。滞在期間中、私はおじさんの部屋には近づけなかった。
滞在期間中、近くに住んでいるおじさんの娘と孫たちが遊びきてくれたことがある。私と歳はほとんど変わらない孫たちは家に上がるやいなや、おじさんのベッドによじ登っては「ジージージージー、あのね・・・あのね・・・」と学校から帰ってきてお母さんに1日の報告をするように、嬉しそうに楽しそうに、おじさんに話しかけていた。そこに何の壁もなく、私はその姿をとても素敵だなと思って見ていた。こんなふうに接していいんだと学んだのであるが、今から急に態度を変えて、「ねーねーおじさん」と話しかけるのはプライドが許さず、やっぱり、私はおじさんには近づけなかった。
小学生のころの記憶なんて、どれもこれも一緒くたになっておもちゃ箱のようにしまってあるんだけど、不思議とこの横浜の記憶だけはすぐ取り出せて、しかもその記憶は真空パックでもしているかのように鮮度も落ちずにいる。
いつぞやの晩御飯のあと、母が渡してきたのは、そのおじさんの手記であった。もらったときにすぐに読まず、しばらく本棚に仕舞っていたのは、あの時、避けてしまった後ろめたさがあったからかもしれない。とびっきり上等な酒を飲んだ昨晩、カランコロンと氷を鳴らしながら読んでみることにした。
手記はこんな言葉から始まっている、「小さい孫たちの名前も呼んでやれないし、頭ひとつ撫でてやれない。不思議に思っていることだろう。やがて物事がわかるようになったときにこれを読んで、事情を理解して、ゆるしてもらえることを願いたい」。手記は41ページあり、ALSの診断を受けた昭和61年から、文脈から想定するに平成4年ごろまで、元気な身体が不自由になっていく様子と取り巻く環境、支え続ける横浜のおばさんの姿が、自身の言葉で語られる。きちっとした文体で、周りへの感謝や気遣いの言葉が多く目にとまる一方で、弱音のようなものが表に見えないところに人柄を感じる。
あっという間に読み終え、とびっきり上等な酒をもう一度口に流し、物思いに耽る。横浜のおじさんと初めて会話したような気分になって、あのとき、鹿児島から来て、自分の部屋に寄りつかない遠い親戚の小学生に何を思っていただろうか。きっとこんなふうに思っていたんじゃないだろうか。そうだよな、こんな文章書くんだもん。きっとそうだよな。とかなんか想像してみたりしてブツブツブツブツ会話をしたのである。







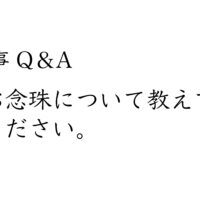
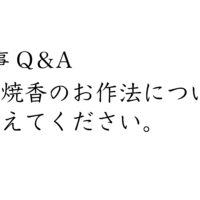
この記事へのコメントはありません。